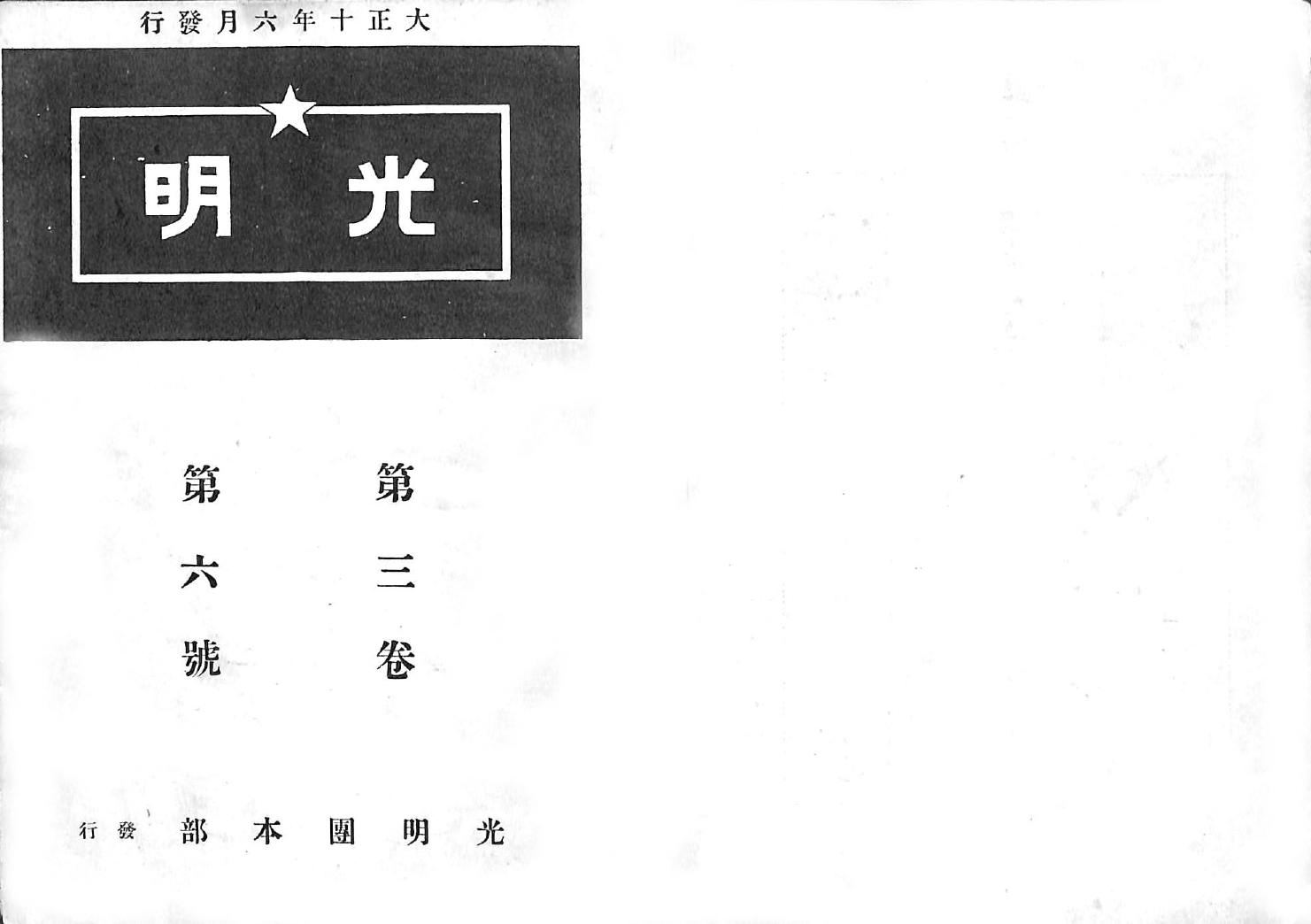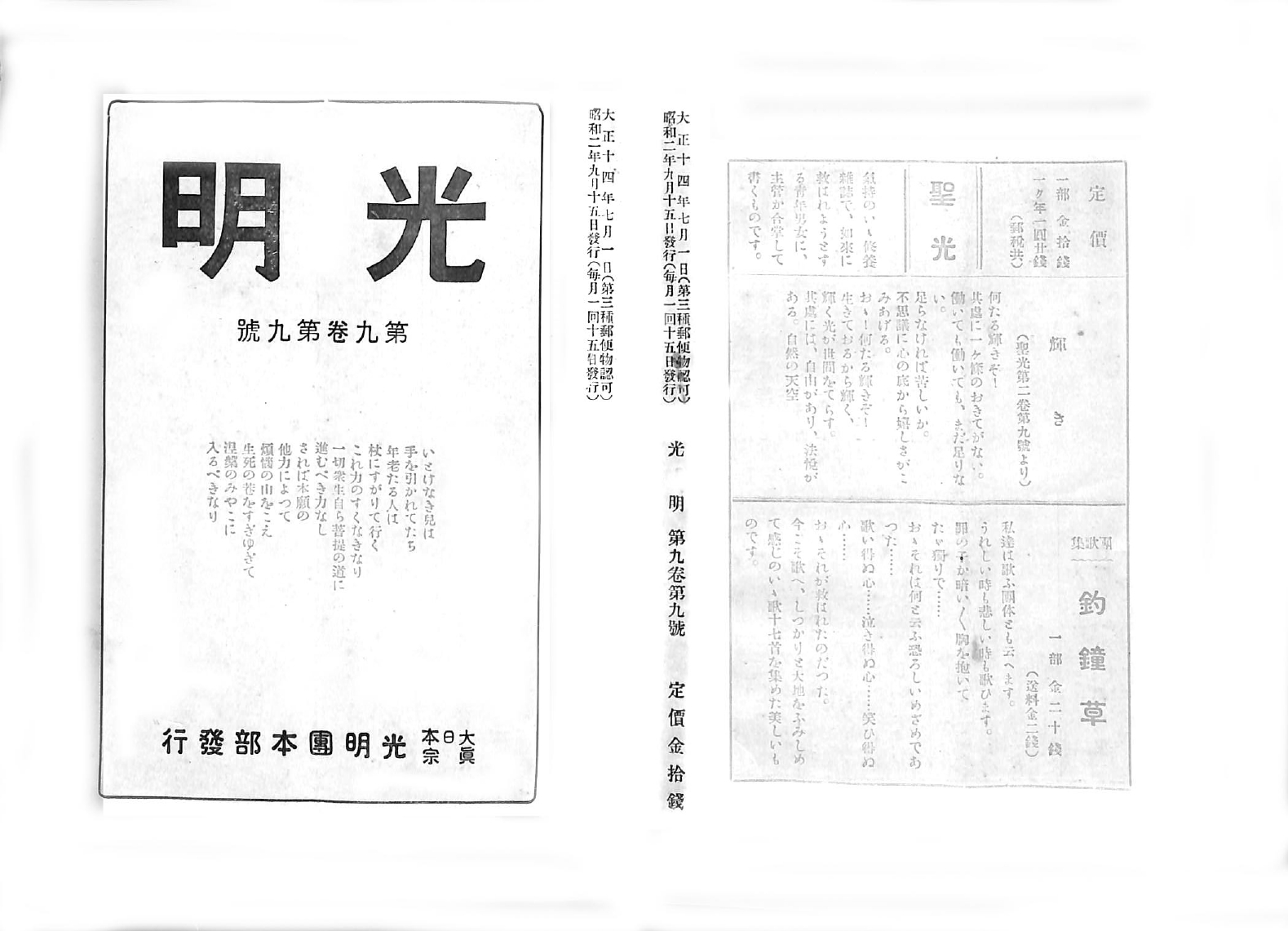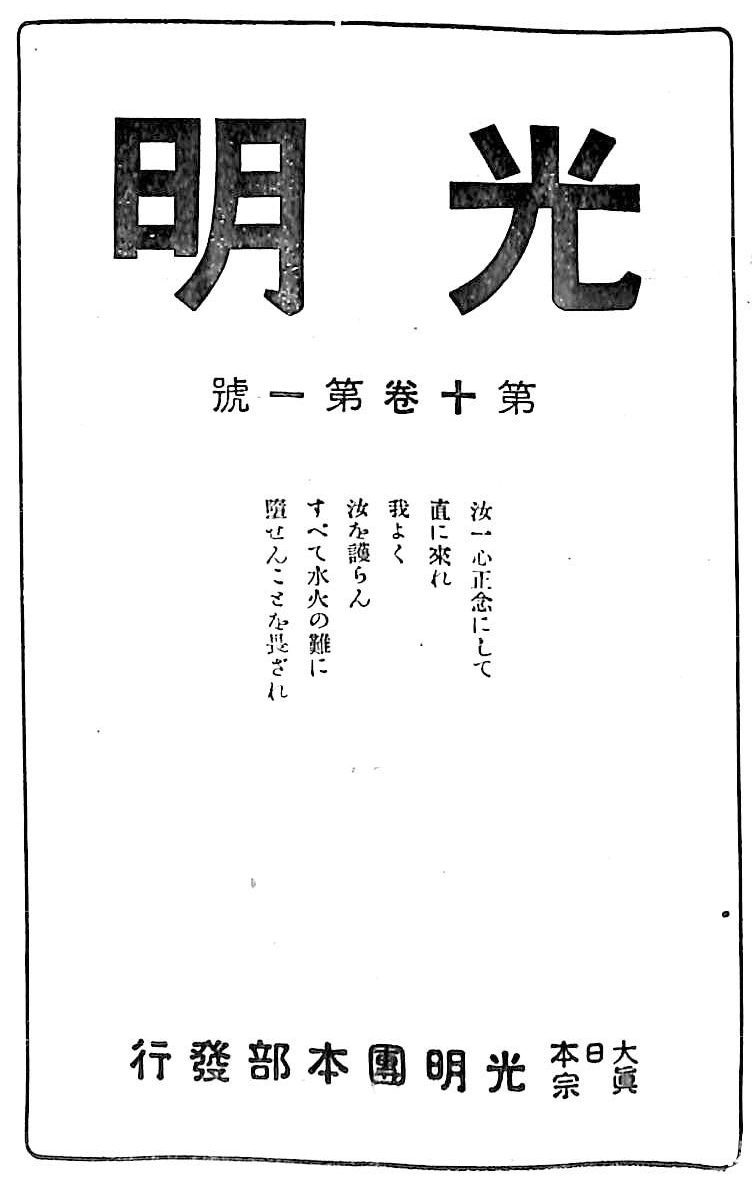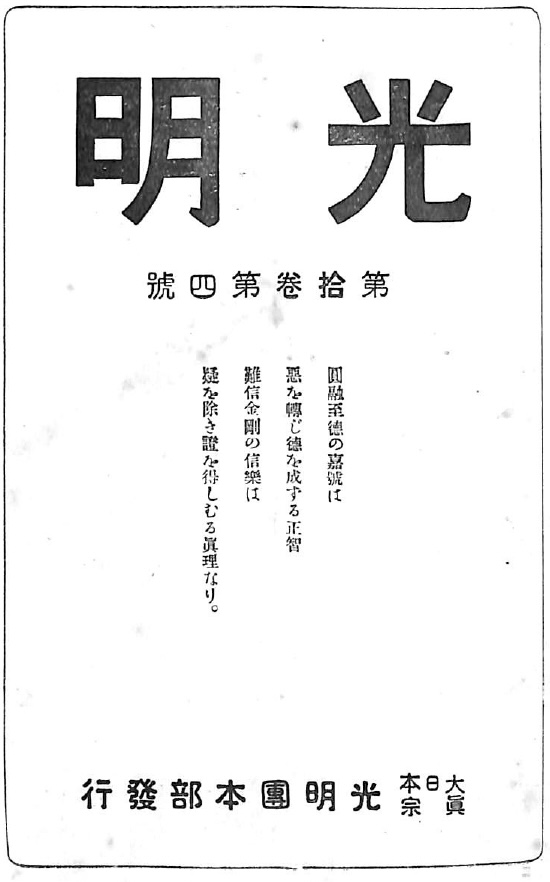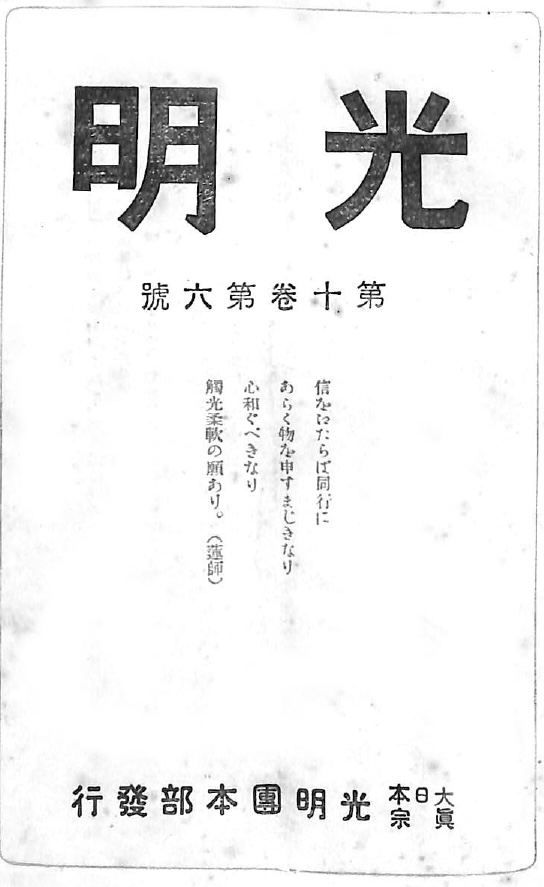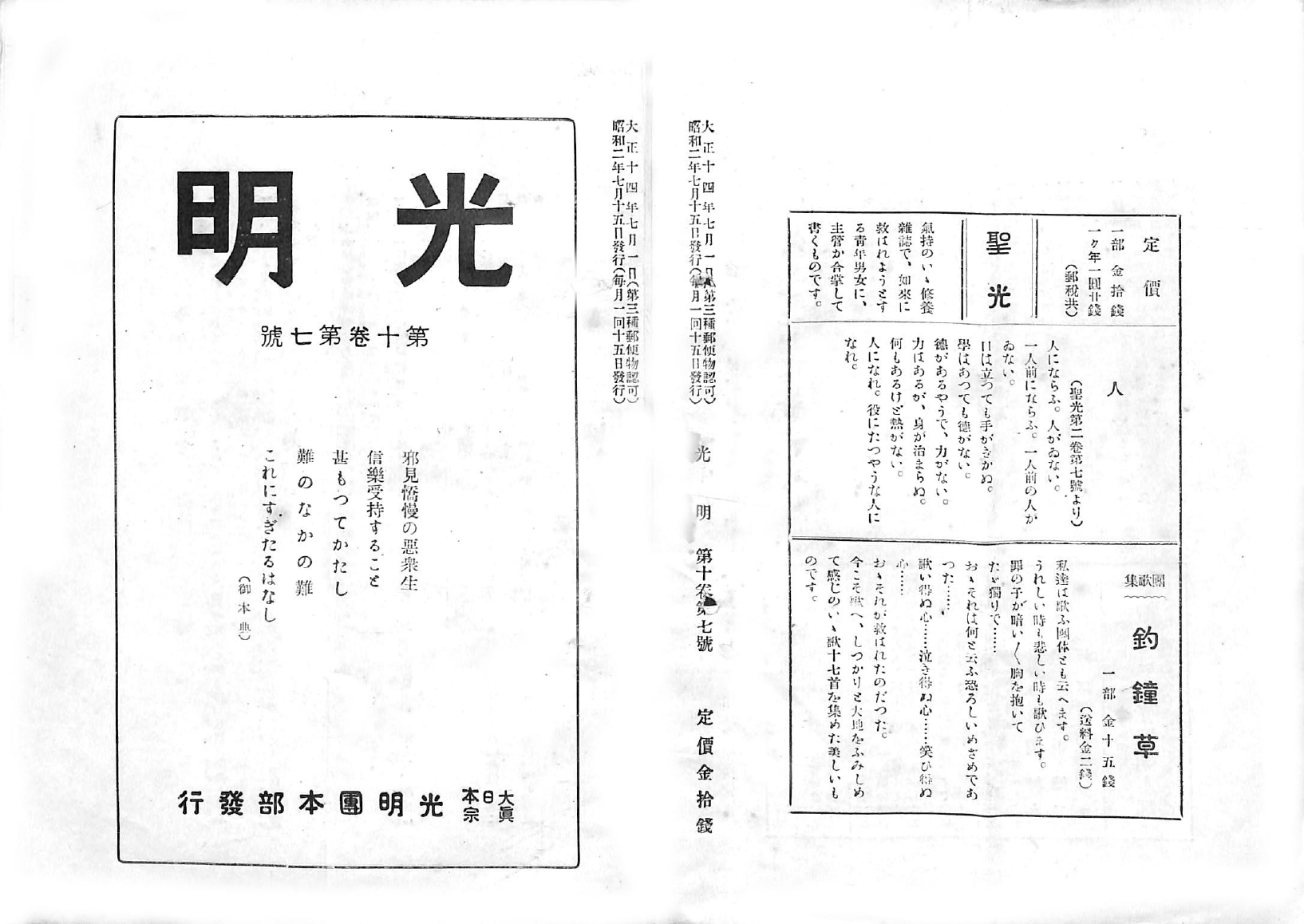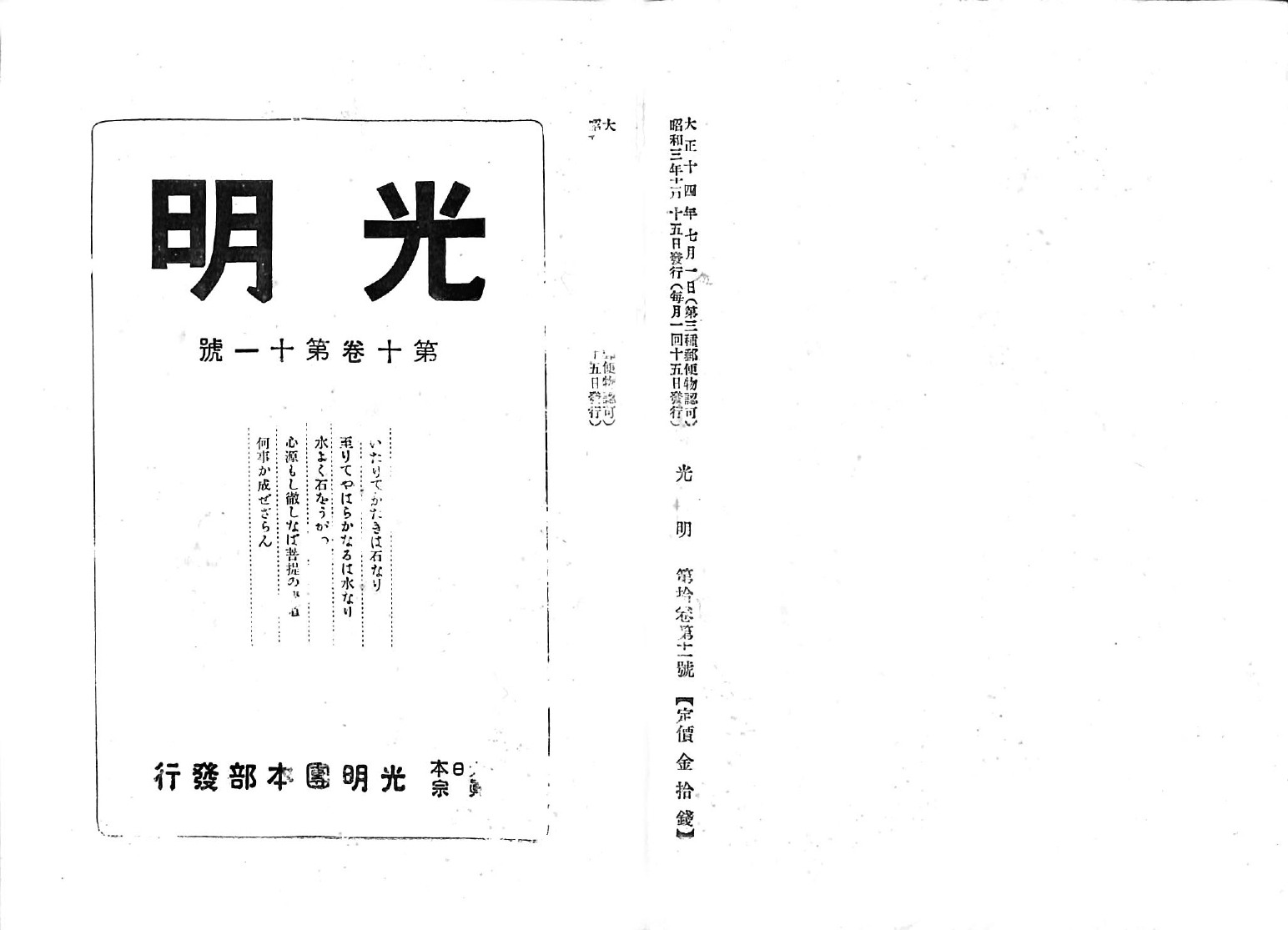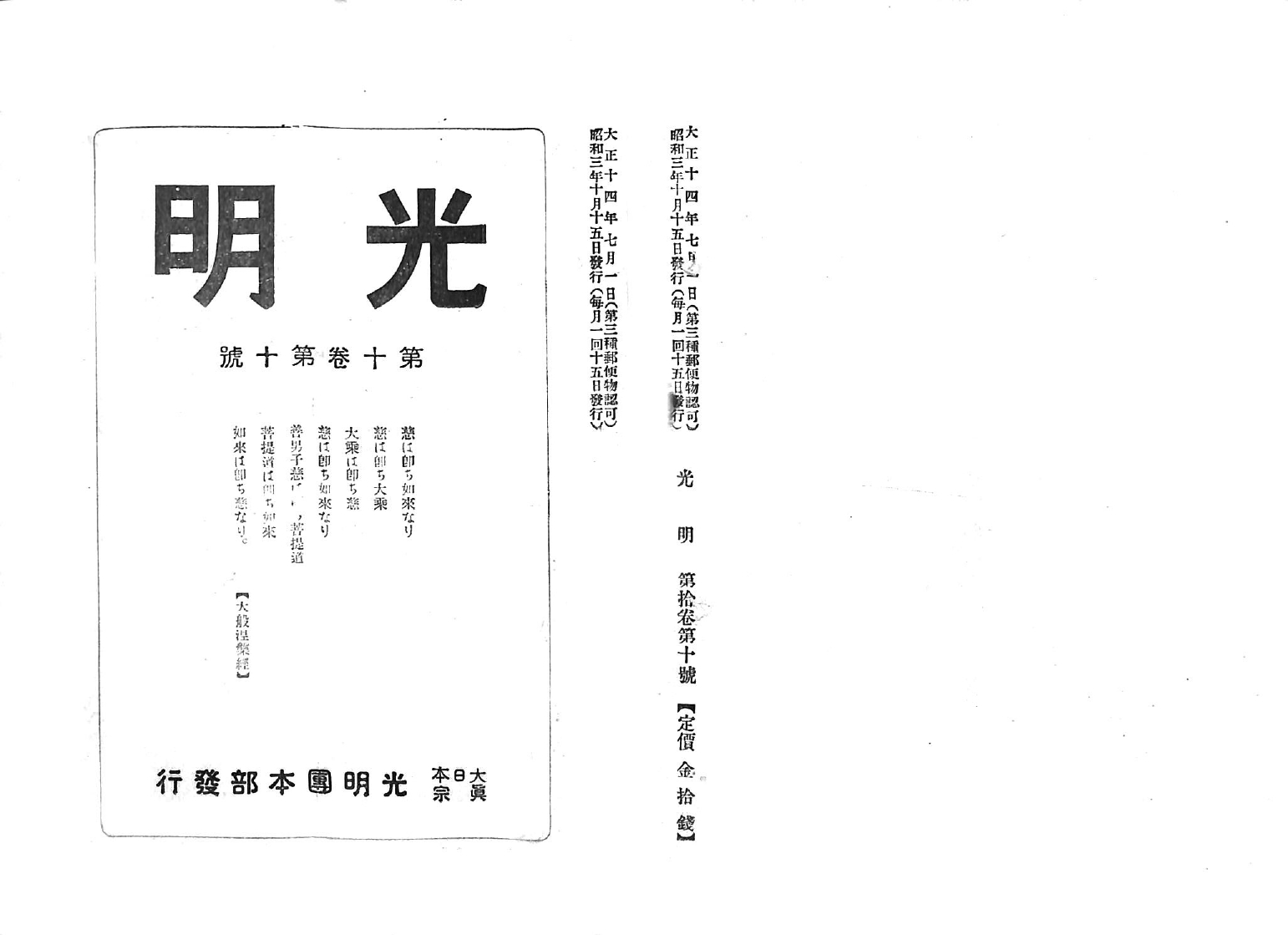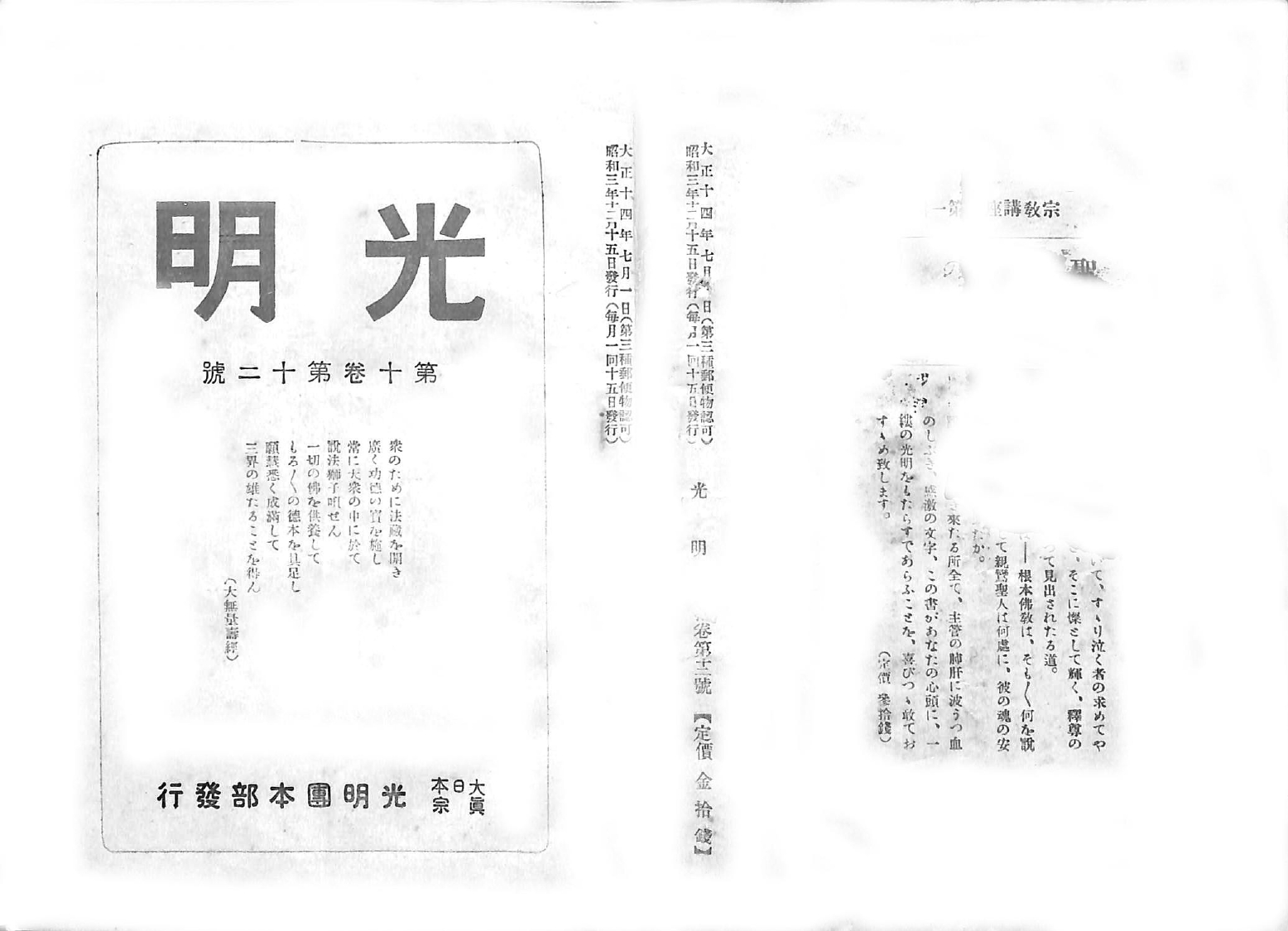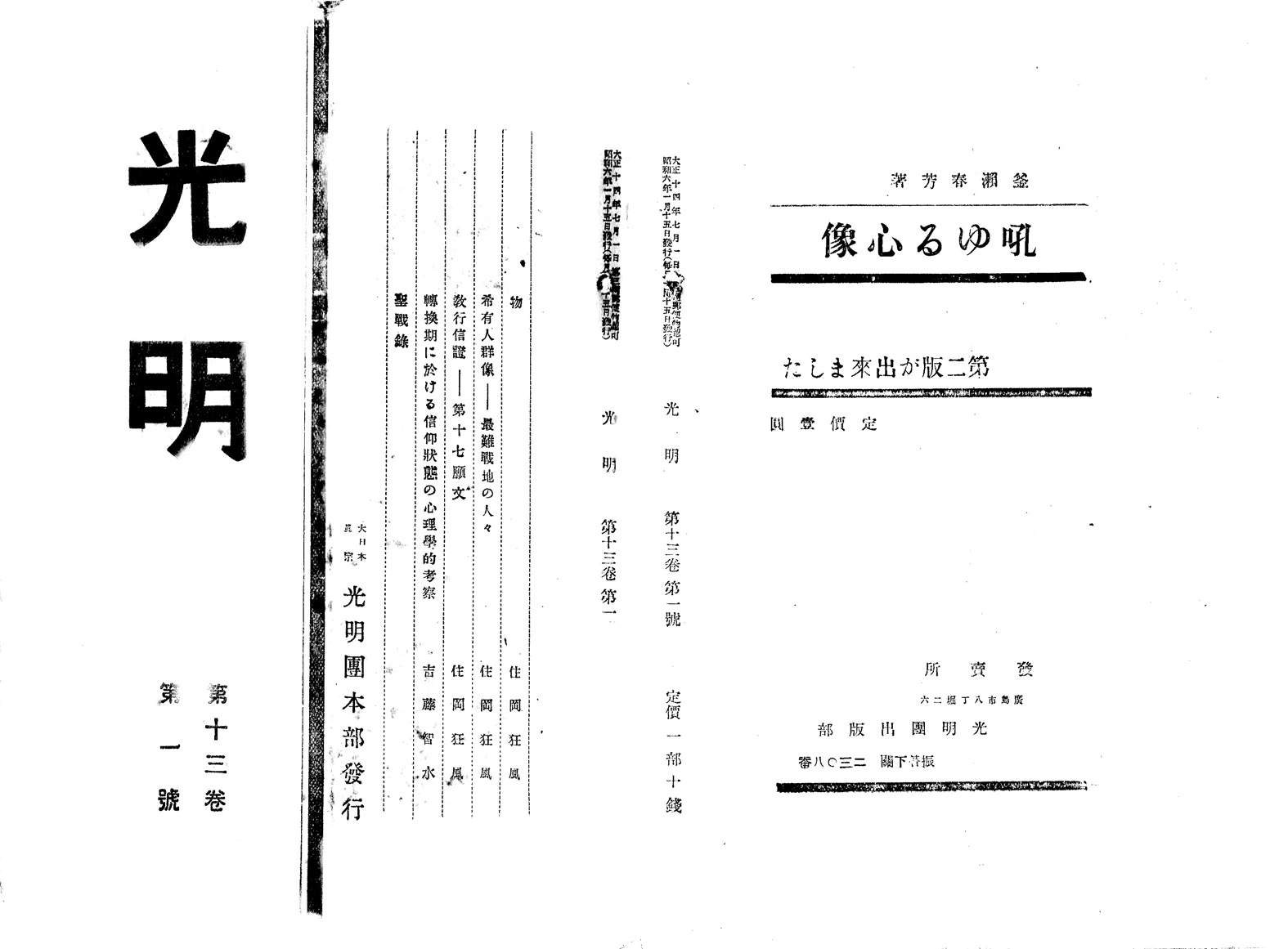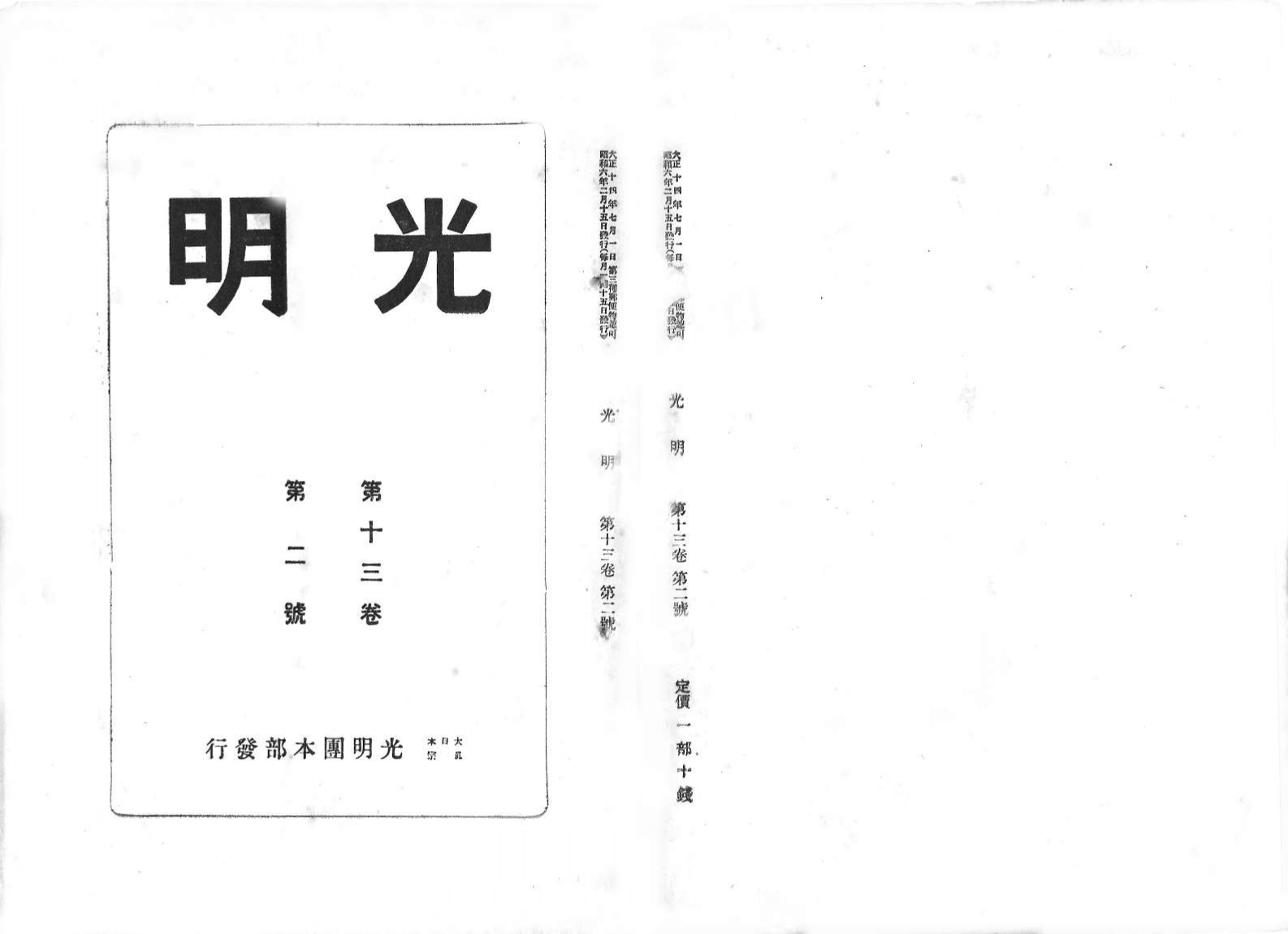『光明』誌 デジタルアーカイブ
住岡夜晃師在世中の『光明』誌を順次掲載します。
『光明』第3巻 大正10年(1921年)発行 夜晃師27歳
光明団がつくられて3年目に発行された光明誌です。
4月に3周年大会が開かれ、その後光明誌は活字印刷となったそうですから、6月号はその頃発行されたもののようです。
今から約100年前のもので、大変貴重なものです。
当時夜晃先生は飯室小学校に勤務しておられました。
2年後、先生は教職を辞し、家族とともに故郷を出られました。
かつては この世を呪ったこともあった
けれど今
ああ何という美しい地上だろう
ああ何という荘厳な世界だろう
見よ! 川も 山も 空も そして全ては
美しく輝ける色彩と 豊醇なる香気と
無量の光明とを以て飾られてある
この地上の栄光を讃美せよ! 驚嘆せよ!
かくのごとく飾られたる地上はこれ祭壇
祭壇に呼吸せる人の子に
全て地上に於ける者を呪い 裁き 運命を軽んじ
自らを汚すことが許されようか
人の子よ! 人の子はこの荘厳なる祭壇に立って ただ仰げ
おおただ合掌して 大愛の尊さに抱かれるとき
汝に不二の白道は示される
進め 白道を ただ合掌して 合掌して
『光明』第7巻 大正14年(1925年)発行 夜晃師31歳
おおそれが生きておるのか
そもそも死んでおるのか
草も太る 木ものびる
寒い寒い冬の日でさえ
堅い堅い年輪をつくるではないか
汝は一体精神的にどれだけのびたか
春の日のような順境には 安価なる享楽の夢に陶酔し
冬の日のような逆境には 忍辱精進の力も失って呪いの死の生存を続ける
生きているなら覚めよ
覚めているなら求めよ
求めて立ちあがらないならば
汝に永遠の道はとざされてある
彼女の聞法三十年
しかし彼女には何物もない
聞くだけが賢いのなら
浪速節道楽の男が一生を寄席に通うて何ほど賢くなったか
一生を聞法に使うてしかも何物もない
どこに欠陥があったか
彼女はただ我を忘れて話を聞いたのだ
我を知らずして話を聞けば 話は話に終わる
話を聞く者は多く 道を求める者は少ない
道を求めて三十年を費やすか
話を聞いて三十年を送るか
往生極楽の話は甘く
往生極楽の道は易くして辛し
『光明』第8巻 大正15年(1926年)発行 夜晃師32歳
1月、長女哲子の死。 2月、二女公手誕生。
4月、本部を広島市八丁堀二六番地に移し、月初め三日間の例会をはじめ、加えて屋外伝導をはじめる。7月、『光明』の姉妹誌『聖光』を発行。
12月、光明団女子青年会を設立。団歌集『釣鐘草』を刊行。
人がそしったと泣くのか
如来のみ声を聞こうではないか
人が疑ったと泣いているのか
如来のみ声を聞こうではないか
迷える人にほめられて地獄にゆくのか
如来にほめられて如来となるのか
芸者にもすかれ 親にもほめられる人であり得ると思うのか
眼を光明界にそそげ
地上十六億の人が皆そしっても
おお永遠にほめたまうみ親を知らぬか
汝に念仏のやまぬかぎり
汝に合掌のやまぬかぎり
永遠に汝は法界の勝利者である
庭の青桐の葉が色づいて今にもおちそう
黄菊白菊が今を盛りと咲きにおう
眼が地上を離れて天空を見つめる
おお何たる偉きさぞ
真青い晴れ切った大空!
そこに一点の曇りもない
眼をつぶる! 幻が浮かぶ
一つ一つ はっきりした顔となって現われる
地上を超えた聖座
そこには永遠に朽ちない過去の聖者たちが綺羅星のように並ぶ
あまりの神々しさに暗くなる胸!
思わず合掌したい心になる
ああ 何も考えずに暮すにしてはあまりにも尊すぎる
物思わるる秋
愛する同胞よ 健在なれ
大正十五年去って大正十六年来たる。
ああ、何たる早さだろう。
合掌して本年中私を愛して下さった幾万の同胞を通して、全人類に感謝し、おわびする。
年去ってただ、南無阿弥陀仏。
年来たるもただ、南無阿弥陀仏。
念々、年々、ただ大心海のうちに生れてゆく。
『光明』第9巻 昭和2年(1927年)発行 夜晃師33歳
あなたは今、ご立派な善人として世の中の賞賛の的である。
あなたは今、お得意の最中です。
何の暗さや寂しさがあろう。
しかし、私どもはあなたからいやな気持ちと冷たさをしか受けませぬ。
苦しみ悩む寂しい人間はあなたからサヨーナラをします。
私どもはあなたに用事はないのです。
あなたの笑いは堂々たるものであります。
しかし私たちはその笑いを見れば寂しいのです。
私たちは人間の苦しさをあまりに知りつくしました。
底なき闇を知らされました。
私はゆきます。
淋しい人の胸から胸に巡礼して・・・
苦しい旅に疲れた人たちの涙から涙に巡礼して・・・
み仏様!
私は今至尊の前にひれ伏して名号をよんでいます
ほめられているのもほんとうの私ではありませぬ
そしられているのもほんとうの私ではありませぬ
念仏して合掌しているこの私のみがほんとうの私であります
至尊よ!
私を召喚あそばす如来よ!
多くの時私はふざけています
たかあがりしたり自卑したり
しかし私があなたに帰命した時 私の心はおちつきます
かぎりなきひろがりとうるおいに 私の心はほほえみます
厳粛な心持が 私に精進せよとささやきます
私は唯あなたによって生かされてあります
自然に 平和に
父永眠す
寂々として我が心楽しまず
語らんとすれど父いまさず
頼らんとすれど父いまさず
されど我が耳底に残る
父いませし日の念仏のこえ
さびしくも我念仏す
念仏の世界に父います
涙の中にも微光あり
父上は今寂光浄土に我をみそなわす
聖人は念仏するのみぞ真の孝なる所以を知らしめたまう
仏前を去り得ず ただ終日父をのみ憶いつつ念仏す
如来がわかれば自己がわかる
自己がわかれば如来がわかる
わからぬものは自己である
鏡を凝視せよ 自己が見える
如来を信ぜよ 大円鏡智にうつる自己が見える
自分のわからぬものに 自分の道があろうはずがない
道がわからぬものには 力と悦びとおちつきのあるはずがない
如来の本願は一切衆生の道である
本願の大道に立ったものだけに
真実のみ国への歩みがある
『光明』第10巻 第1〜6号 昭和3年(1928年)発行 夜晃師34歳
聖人様。雪が降ります。綿のような雪が降ります。雪を見ると私は私の生まれた故郷の冬の日を憶い出します。雪の降る冬の日の故郷は、報恩講の営みやご正忌など、み法の相続に恵まれています。雪を見、故郷を思い出す時、私はあなたのことをしのびます。
一月十六日、それは、あなたが生死の苦海からあの世へと往生あそばした記念日であります。本年もまたそのご正忌が近づきました。
(「御正忌を迎える心」より)
冬である
万物のしいたげられた冬である
しかし眼をするどくして見るがいい
枯れた小草の間に
吹きさらされた小枝の先に
強い強い生命の力が動いているではないか
ふくらむ梅のつぼみと共に
春のめぐみは大地の底深く動きつつあるよ
生きる者の心は躍る
願力……それは群生の上に回向されためぐみである
(「巻頭の叫び」より)
生きる者の心は躍る
見よ群生の上に春は輝く
花も咲くだろう
小鳥も歌うだろう
されど散る花に無常を感じた人もある
花の咲くのも束の間である
盛なるものの裏に哀愁かくれ
死滅の裏に永生あり
栄枯盛衰は因縁の仮相
真如…如来…南無阿弥陀仏…
如来の願力のみ永遠の大生命にてまします
何を思うや散る花の木陰に
人生の旅につかれた男がある
何を思うや 散る花の木陰に
何を考えるや 響く夕の鐘の音に
何かしら心の扉の窓をたたく
孤独? 哀愁?
その寂しい胸をどうしようとする
左には酒と女とが待つ享楽の巷が
右には 悲観 家出 自殺 人生逃避の暗黒の淵が
その中間にも道がある 極めて狭く見える
進め! その中道を 苦をいだきしめて
よし如何なる苦悩が横たわっていようと
足をかけたら今まで聞いたことのない声が聞こえる…南無阿弥陀仏…
人間が人間の問題でゆきづまった時
人間の技巧によっては決して解決しない
人間のはからいは 逃げること
移ることによって解決したように思う
はからって浮かぼうとする所に
醜い第二第三の苦悩を生み出す
人間の問題の解決は
更にこれを自然の声に聞かねばならない
み法は決して個人の所有ではない
如来の血液である
信は如来へ通ずる扉である
人間の問題の解決!
そは如来の願心の内にのみ動いている
信仰は人間の問題の究極的解決である
一事に専心なれ
桜の木は桃の木の真似をしない
親鸞聖人は釈尊の真似をしたのではない
桜の木が万物に桜の木になれとは言わない
一事に忠実なれ
洗濯するときに料理はできない
作すことは一事である
しかし その中に動くものは全人格である
念仏一つに生きる
それが全人格の動きである時
我等はそれを救済と言い 信念とよぶ
『光明』第10巻 第7〜12号
またしても我慢が頭をもたげる
我慢が出ると如来がかくれる
他人の世界の攻撃がはじまる
たとえ人の世界が悪かろうと、攻撃する時には不純がある
我慢が見えたら恥しうなる
私はついに如来の前に頭があがらぬ
小慈小悲もなき身よ
如来の願力に立てば限りなく見ゆる 逆謗の死体
ああ、祖聖よ!
聖人もまたこのなげきを持ちたまふ
如来に帰る日、懺悔はそのまま静かなるよろこびである
一すじの道あり
この道 現実より浄土に通ず
一切群生無限の苦悩の底に
静かに必然に流るる至純の業力
処を超え 時を超え 人を超えて
永遠に輝くたった一つの本尊
滅ぶべき一切の群生を乗せて
永遠の浄土にはこぶたった一つの力
この力 全人格の上に動けば これを「信」という
如来は信なり
我も信なり
彼我一体の信
ここに永遠の生命動く
私は今たしかに生きている
何をすればいいのか
私にもやがて死が来る
このまま死んでも悔いはない
こうした衷心の願求に答えるものは何か
それは「真実の教」である
真実の教は決して人間の便宜で作られたものではない
如来の胸底から流れ出た聖なるみこころである
我が前に立ちます善知識こそ
この聖なるみ旨を伝えたまう仏の使いよ
合掌して受けん 聖なるみ旨を
我が胸底に信の血が動く
白銀の明鏡 東の山をはなれ
天空 黒く澄んで 星まばらなり
白露光る所 虫の音 天の楽を地に奏す
これを眺め これを聞き これを喜ぶ者幾人かある
久遠の真如の月 一切群生の上に光る
これを眺め これを嘆美する者いくばく
独り月下に合掌し 念仏する
この心寂しく この心哀れなり
ああ 何ぞ薄俗非急の凡事に囚われて
この明鏡を仰がざる者の多き
友はあらざるか
一人見んにはあまりに尊きにすぐ
(九月二十六日小用の浜にて)
「十周年を迎えて」
粗末な田舎の小学校の宿直室に、たった一円出した貧弱な机があり、古ぼけた火鉢が一個、ほかには書物がたくさん立てたり積んだりしてあるだけです。
彼は淋しいのです。長い孤独な寂しい生活が続いたのです。
その寂しい生活の唯中にたった一つの念仏が生れました。
重いからまる鉄鎖にくくられた宿業の子は、単純に生きてゆくには、あまりに恵まれていませんでした。
日が暮れる 何だか寂しい
年が暮れる 何だか寂しい
暮れる時 何人も久遠の凡夫である
疲れた 暗い 悲愁の胸に響くは一体何の音か
静かに我にかえって考える時 合掌の胸に念仏がある
願生の夕べ 沈黙の胸に聞こゆる声は一体何か
ひしひしとせまる哀感の中に
紅にそむ西をながめて
霊の故郷に通うこの心
日は暮れてゆく
静かなる願生の夕べよ
『光明』第13巻 昭和6年(1931年)発行 夜晃師37歳
光明スピリット
その静かなること 林の如く
その速きこと 風の如く
侵略 火の如く
不動 山の如し
大信に生きる我等の生活は
生死動乱に処するに 風の速さを用い
濁乱の世に内外の悪魔を侵略するに 火の熱烈に習い
困苦逆境に立って 山の如く動かず
これはこれ光明団スピリット精神!
これ真の力の人
合掌念仏すれば 仏 我が内に白熱したまう
暗黒をなげくよりも
汝の内に智慧の燈を揚げよ
冷たき心 怒りの情は
汝を地獄の底に滅ぼす
道は横臥して幻想を弄ぶ者に開けず
断然起って行え
断じて行えば鬼神も避く
智を磨け
情をやわらげよ
意志を強くせよ
断じて行う意志なき者に 偉大なる人生なし
愚かなる者に 明るき人生なし
温かき心情なき者に 楽しき人生なし矣