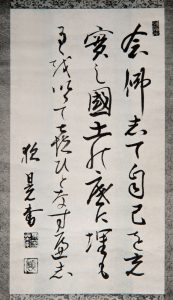夜晃先生のご教化の特色
ここで夜晃先生のご教化の特色について触れたいと思います。先生は在家のご出身であり、しかも学校の教師の経験を持っておられたために、従来の伝統的な伝道方法に縛られることもなく、新しい独自な方法を編み出していかれました。その中で特筆すべきものを紹介すると、次のようなものです。これらは、今日ではお寺でも普通に行われるようになりましたが、当時、昭和の初めには全く画期的なことでした。これらも光明団が異端視された理由の一つでした。
黒板の利用
先生の講義は常にお聖教(経・論・釈)にもとづいてなされ、主題とその原文、要点を黒板に板書するという方法で為されたため、講義の筋道がはっきりして理解しやすいものでした。当時のお寺のお説教は、聴衆は説教師の話をもっぱら聞くだけで、黒板を使って講義されるようなことは全くなく、板書された文字を見るといったことは皆無でした。また聞き手は、板書された文字を自分のノートに写すことが当たり前となっていたので、講義の始まる前には、必ず大広間に、座って筆記することの出来る低くて横に細長い机が並べられました。この方法によって分かることは、聞法もまず学習であるということです。

聖典の活用
同胞にはすべて浄土真宗の聖典(島地大等編・明治書院)を持たせ、講義の時は、常に聖典の該当箇所を開けさせ、原文を押さえて話を進められました。これは講義内容の根拠を明らかにすることによって、仏法の領解が主観的情緒的になることを避けるためです。先生は聴衆の感情に訴えるようないわゆるありがたい説教よりも、客観的な、論理的骨格を持った講義を重視されました。しかしそれは、決していわゆる学問を中心とした観念的な講義ということではありません。どのような人間も愚かな凡夫に目覚めない限り本願に乗托することは出来ないという本願による救いの道理を徹底させること、すなわちどこまでも真実の自覚を成就するための講義でした。聞き手は聖典の大事な言葉には印をつけ、またノートにも書くので、決してその場限りの聞法にならず、復習するなど、必ず後に生きてくるようになっていました。
寺院を中心とする従来の聞法は、聖典も持たず、ノートもとらないで、ただ惚れ惚れと講師の説教を聞くということが当たり前であり、それが他力の意にかなう聞法と思われていましたので、夜晃先生が取り入れられたこのような方法は、全く異質なものと受け取られたようです。
座談の重視
夜晃先生は午前午後の講義のあと、必ず一時間ばかりの座談の時間を設けられました。説き手は説きっぱなし、聞き手は聞きっぱなしのお説教しかなかった当時に、このような座談を設けるということは従来の聴聞の伝統を破るものでした。これは先生亡き後も光明団の伝統になっていて、現在でも、どの会座も講義(聞法)と座談がセットになっています。大きな講習会の場合、座談は十名以内の小グループで行われる班別座談と、全員が集まった中で、夜晃先生と聞き手が一対一で対座して行われる合同座談と二種類ありました。
班別座談では、少人数ですからお互いに心を開いて、よく分からなかったところを話し合って、聞いた教えの中心点を確認したり、自分の現実(問題)との関係を考えたり、先輩の底の抜けた仏法讃嘆を聞くことで、各自の仏法の理解を深め聞法の意欲を高めることが期待されました。特に初心の人の関心と質問が大切にされることはいうまでもありません。
それに対して合同座談は、班別座談では解決しなかった信心と念仏の問題について、夜晃先生と質問者が真剣に向き合って問答し、ついに迷妄の根源が翻される場として設けられました。すなわち、〝如来生きてまします〞と、如来の前に徹底して頭を下げることができるかどうか〝念仏一つで事足りる〞と言い切れるかどうか、それはまさに《如来が勝つか煩悩が勝つか》という真剣勝負であり、その場の雰囲気は緊張に満ちた厳しいものでした。
この座談の重視は、すでにして中世の蓮如上人の強調されたところであり、仏法が一人一人の身につくためには欠かせない方法ですが、ともすれば座談が軽視されるのは、当時でも今日でも変わらないようです。
先生の講義の内容は、「浄土三部経」をはじめ、「教行信証」「正信偈」「浄土和讃」「歎異抄」など親鸞聖人のもの、また「大乗起信論」「浄土論註」「観経疏」などの論釈書もあって、多岐にわたっていました。何よりも原典を重んじられ、漢文を黒板に板書して進められる先生の講義は決して易しいものではありませんでしたが、先生は前の方に座っているお年寄りを大切にされ、巧みな比喩などを用いて、お年寄りが喜んでうなづくことのないような話はされなかったそうです。それは一見どんなに難しい教えも、先生自身がそれをお念仏の内容として有り難く頂ききっておられたからこそ可能だったことでしょう。どんな講義も、それがお念仏をこころ(意)を明らかにしていて下さるものと分かればうなづいて聞けるのですね。
しかし原典に忠実に一句一節を大切に頂いていかれる先生の講義について、「あれは理屈だ。ご信心にはむつかしい理屈はいらない。ただ信じさえすればよいのではないか」という世間の批判がありました。このような批判(非難)に対して、先生のお考えははっきりしていました。
「ただ信じればいいのなら何を信じてもいいはずだ。何を信じればいいのか、如何に信じればいいか。親鸞聖人には極めてはっきりした論理があり、骨格があった。」「その正しい論理のない信心が、結局現在のあのだらしのない教界の空気を作ったのであり、青年及び知識階級を追い逃がしたのではないか」
夜晃先生のご教化には常に燃えるようなあつい熱がありましたが、それは冷たい論理の骨格によってしっかり裏付けられていたことを忘れてはなりません。
(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)