15周年大会と本部の建設
昭和八年十二月、創立15周年の記念講習会が広島市内の八丁堀の本部(借宅)で開かれました。先生の回顧文によれば、街に宣伝もせず、5周年や10周年の時のような賑やかさもなく、人数も五十名余と比較的少なく、形の上では極めて地味で静かな五日間の講習会であったけれども、しかし今までにない真剣で充実した空気が流れていたと述べておられます。先生の講義の内容は道綽禅師でした。
この15周年大会について、先生は「この大会こそ、一面過去の団の歩みを清算するものであり、一面将来への飛躍の第一歩を画する一大基調をなすものであった」と総括され、光明団僧伽の今後について確かな手ごたえと自信を得られたのでした。そういう点でこの昭和八年 (一九三三年)は、光明団僧伽が草創期の不安定を脱して本格的な伝道活動を展開していくための大きな転換点の年であったと言うことが出来ます。
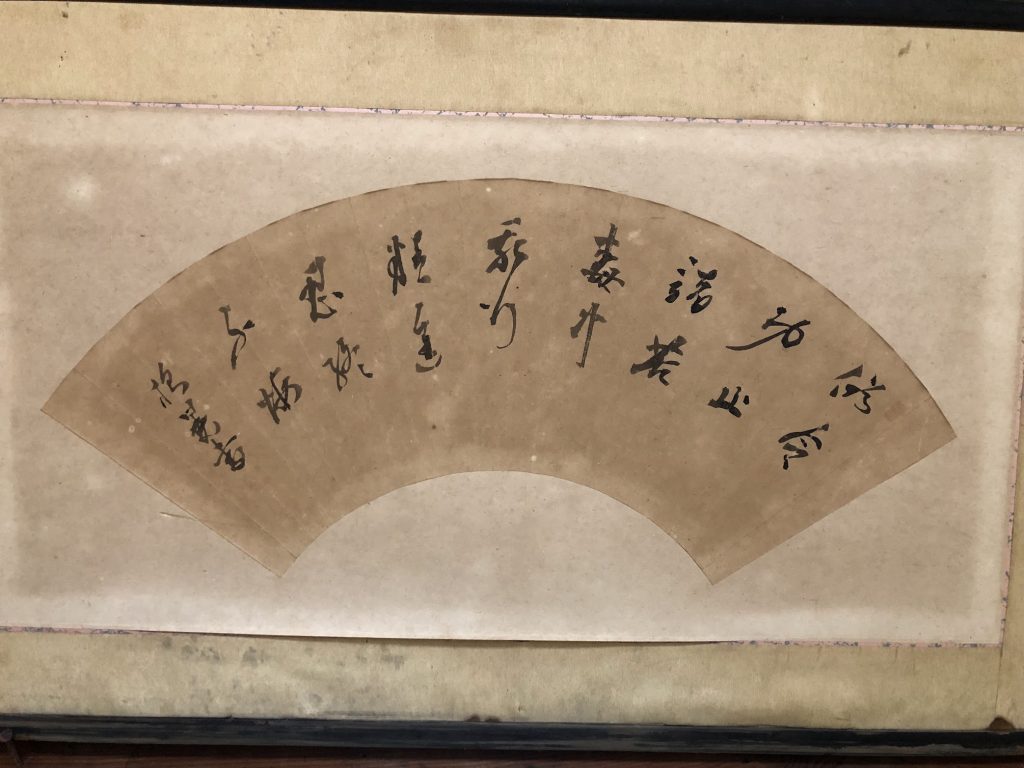
その15周年と揆を一にして、かねての懸案であった新本部の建設が着々と進行しました。場所は広島市内の庚午町五一九番地で、現在の本部の場所です。規模は、六間に十三間の総二階、七十五畳敷きの講堂をはじめ、本部員の居室十室等を有する木造の堂々たる建物です。(一間は約一・八メートルです)
この建物は、棟梁 柳川富太郎氏によって造られました。彼は夜晃先生と光明団の活動に深く共鳴され、全くそろばんを離れて誠心誠意、献身的に尽力されました。当時のお金でわずか4,500円で仕上げられたとのこと、今日のお金に換算すればどれくらいになるのかわかりませんが、これくらいの費用ではこれだけの規模の建物はとても建たないのではないでしょうか。また団員の吉見又一さんも建設委員として、本部建設のために自分の仕事をなげうって東奔西走して下さり、先生はこのお二人のご苦労なくしては本部の建設はありえなかったと深く感謝しておられます。新築なった本部への移転は、15周年大会後の、年末に行われたようです。
考えてみると、創立以来15年間、「光明団」は自前の本部(道場)を持たないままで借家を転々としながら活動をしてきたのでした。その不便さ不自由さは推して知るべしです。夜晃先生とご家族の安堵と喜びはどんなに大きかったことでしょう。特に、濁乱の世に真実仏道を明らかにせんとの先生の念願は、ここに新しく本拠地を確保されたことによって、ますます強く、地についたものになったに違いありません。組織論からいっても、本部がしっかりして本部の機能を果たすことなくして支部の活性化はありません。先生が巡教の旅に出ておられる時も、奥さんを中心とした何名かの本部員がしっかり先生の留守を支えて本部を守ったことが団の発展につながっていきました。
夜晃先生が光明団を創立されて、やがてご往生されるまでの期間は約三十年でしたから、創立15周年は丁度その中間点にあたるわけで、マラソンでいえば折り返し点です。したがってこの後半の十五年こそ、夜晃先生の光明団の最盛期といえるかと思います。 目を外に向けると当時の日本は、次第に軍部の勢力が増大して満州(中国東北部)を侵略し、国際連盟を脱退するなど、日本の国際的孤立化が進んで戦争への足音が段々高くなってくる重苦しい時代でした。
(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)


