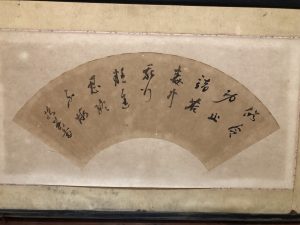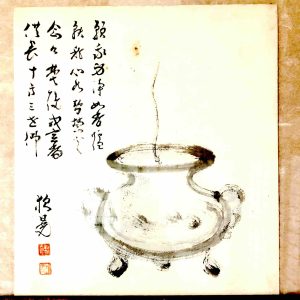本部会座の充実
創立十五周年を終え、本部建設成った翌年の昭和九年(一九三四年)、 先生は数えで四十歳を迎えられました。四十歳といえばいわゆる不惑の年です。人の一生の中でも一番精気あふれる仕事の出来る年です。先生はその「不惑」に関して、ご自身については 〝不惑どころかいよいよ名利の大山・愛欲の広海に迷惑・沈没しているわが身である〟と深く懺悔されると共に、仏道の歩みについては、〝惑どころかいよいよ如来・本願の真意を頂いてこの道をしっかり歩み通したい〟と述懐しておられます。それは、この年から四年間、『光明』誌に「如来本願の真意」と題した先生の本格的な本願の領解を連載されたことを見ても分かります。
新しい本部・道場が出来たということは、まず何よりも本部の会座が充実するということでした。これまで長い間、本部といっても有って無きが如しで、毎月の例会以外の長期間の会座はほとんど開かれませんでした。先生は専ら各地を回って伝道の旅を続けておられましたから、本部で腰をすえてじっくりお話されることはあまりなかったのではないかと推測されます。
昭和九年、木の香もかぐわしい新築されたばかりの本部で、先生は一週間という長期の講習会を二つ始められました。一つは八月一日から七日までの夏季講習会であり、もう一つは、十二月一日から七日までの報恩講講習会です。夏季講習会は昭和六年に鳥取の東郷温泉ホテルで開かれた一週間の幹部講習会を原型とされたものでした。(昭和七年、八年も場所を変えて開かれています)。報恩講講習会は今まで十二月初めに開かれていた三日間の報恩講会座を一週間とし、これも毎年定期的に開かれるようになりました。
そしてその翌々年の昭和十一年より、三月末から四月初めにかけて、やはり一週間の春季聖講習会を始められましたから、これでいわゆる「三大講習」といわれる年三回の長期講習会がそろったわけです。

今後この本部の会座は、毎月初めの三日間の例会とこの三大講習会が柱となり、その後夜晃先生がご往生された後も、ずっと毎年続けられていきました。もちろん夜晃先生がご在世の時は、先生がお一人で全部担当されましたから、先生のご苦労のほどは察して余りあるものでしたが、このような充実した本部の会座を通して、先生のご教化が団全体に徹底していったのでした。
夜晃先生によって始められたこのような三大講習会は、他の教団にほとんど例がないもので、聞法の徹底を何より重視した本団の特色がよく現われています。夜晃先生が逝かれてすでに六十年近く経ち、三大講習会は中々困難になって来て、夏季聖会はやむを得ず五日間と二日少なくなったものの、他の春と冬の報恩講講習会は、先生ご在世の時と同じように現在も七日間行われています。
仕事や家庭を持っている人が、世間の時間を削り取って七日間本部で寝食を共にして聞法することはとても困難なことですが、もし出来たならば、その感動は計り知れないほど深いものがあります。聞法といっても、一日はもちろん、三日間くらいの聞法では本当は徹底しないのですね。仏法が本当にわかりたいと思うならば、少なくともこれくらいの時間を聞法に集中する必要があるといえるでしょう。現役の仕事を終えられた定年の方がどんどん増えている高齢化社会の時代にふさわしい聞法のあり方ではないかと思います。
(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)