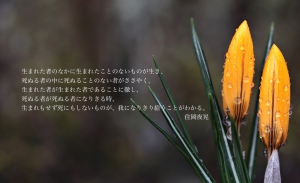十方衆生
「設い我仏を得たらんに………」と誓い給いし法蔵菩薩は、直ちに「十方衆生!」と一切衆生を招喚していられる。
四十八願ことごとくが、聖なる如来願心の表現ではある。
しかし、第十七願までにおいては、第一の無三悪趣の願をはじめとして、六神通の願、さらに第十一願必至滅度の願、十二・十三の光明無量、寿命無量の法身成就の願、やがて十七願、諸仏称名の願等の、極めて重要なる諸願を聞いたけれども、「十方衆生よ」との親心は、はじめて第十八願に出てきたのである。
思うに、如来真実の本願は十方衆生を救済することが、その生命でなくてはならない。
であるから、その因位法蔵の本願は十方衆生の上に立てられなくてはならない。
今、如来はその正覚成就が直ちに十方衆生のためであり、十方衆生をその内容としてのみ如来の正覚成就が可能であることを、直ちに端的にあらわされたのである。
我等は、この如来の願意をいかに領解(りょうげ)すべきであろうか。
思うに如来は、十方衆生に何ものかを求め、何ものかを与えて、衆生と如来とを根本においては一如一体なるものたらしめて、衆生をして如来の眷属(けんぞく)たらしめ、それを通して如来の荘厳浄土を可能ならしめたもう願意でなくてはならない。
しかるに一切衆生は、果たしてかくのごとき自覚を有する衆生であらうか。
衆生が貪欲を生命とし、我執を本性とする以上、個々の衆生はそれぞれ対立分離して、尊き何ものをも成就しようとせず、特に我執はそれ自体が正法に反逆し、いわゆる五逆誹謗正法(ごぎゃくひぼうしょうぼう)の無間業(むけんごう)を造るものである。
しかし、かくのごとき群萌も、如来の願心にさめて如実の衆生たらねばならない。
親鸞聖人はこの如来の招喚の願意にさめて念仏せられたのである。
真に仏を念ずる衆生こそは、如来久遠の願意に目覚めたものでなくてはならない。
十八願における衆生とは、実にかかる衆生のことである。
如来の招喚にさめたる衆生のことである。
親鸞聖人はこの如来招喚のみ声にさめて、
「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずればひとえに親鸞一人がためなりけり」
と告白せられた。
如来は「十方衆生」と誓い、聖人は「一人がため」と領解せられたが、この十方衆生と一人とをいかに考えたらいいのであろうか。
世間の通俗者流の中には、「如来が、汝の傷つけ痛めたる十方衆生の呪いは、この親が引き受けたぞ!と言われることである。十方衆生を引き受けて下さるから、私一人が助けられるのである」との説をなす者があるけれども、それでは再び私は責任回避、因果無視の外道の野にさまようことになる。
又、一切衆生の中の我以外の全てを引き受けられたところで、我一人の全てはいかになるのであるか。
憶うに、いかなる八万四千の経説も、菩提樹下における釈迦自証の一念を離れては何ものもあり得ない。
すでにその自内証の風光である。
大無量寿経もまたこれを離れてはなく、したがって如来の本願もしかりである。
聖人が、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり」と、告白されたことも、それは信の内的風光であって、如来の「十方衆生」の招喚と一致するものでなくてはならない。誠に我(が)に囚われたる衆生の欲心は、決して「十方衆生よ」との声を喜ばぬものである。
「あなた一人」と呼ばれることをこそ喜ぶのである。「あなた一人を」と呼ぶ声は愛である。又それを喜ぶ心もまた愛である。我等の内観の世界において煩悩の声を聞く時、容易に知ることが出来るのは、いかにこの愛に渇(かわ)けるものであるかということである。
龍樹はすでに、『十住毘婆沙論』の巻頭において、
「愛に随える凡夫、無始よりこのかた常に其中に行じ、生死の大海に往来して、未だ曾て彼岸に到ることを得ず」
と断じている。
愛に随うとは、「あなた一人」と呼び、「あなた一人を」と呼ばれることを求める心である。
聖人の「親鸞一人がため」とは、この愛の心であったであろうか。
何人と雖も、否と答えるであろう。
しかるに衆生の欲心は、決して「十方衆生よ」との声を喜ばぬものである。
「あなた一人を」と呼ぶことを真実と思い、「あなた一人が」と呼ばれることを嬉しく思う。
しかし、それは愛であって、真実の慈悲ではない。
愛に随うところに、凡夫の無始永劫の流転があるとの龍樹大士のみ言葉をも引いておいた。
誠に衆生の貪欲は、我一人において利益し、享楽し、権勢を求め、異性を求め、集め集めて我の満足を求めようとする。
「あなた一人が」との囁(ささや)きは、天上の声の如く響き、「あなた一人のために」との声は、渇ける喉に水の如く入り易く受け易いのである。
しかも、かかる声はやがて必ず飽き疲れ、傷つき悩み、より深き渇愛へとつれてゆく。
これ龍樹が、「愛に随える凡夫、無始よりこのかた常に其中に行じ、生死の大海に往来して、未だ曾て彼岸に到ることを得ず」と説き給いしは、いかに愛の心の深いかを内観し給いし告白の声ではあるまいか。
この愛の世界は、純粋な満足を与えるものではない。
一歩あやまれば、量り知られぬ無明の深淵にとつれ込まれる。
そこでこの大地の愛について深い反省がおきてくるにつれて、別なる世界を求めはじめる。