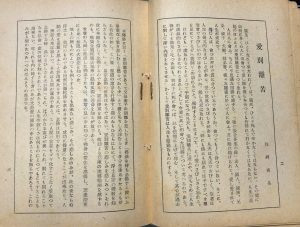離郷と生活上の苦難
同じ年の大正十二年十二月、先生は数十年住み慣れた故郷を離れて、老境を迎えられた両親と弟妹三人を連れて、広島に移られました。家屋敷、田畑、家具等を売り払って資金を作られてのことです。先生はこの一年に、教職を離れるだけでなく、さらに郷里を離れるという決断をされ、実行されたのです。先生にとって、この年がいかに大変な一年であったか分かります。それは先生を全面的に信頼して、先生の決断に黙ってしたがっていかれたご両親、特にお母さんの理解と決断なくしては不可能なことでした。
なぜ一家をあげて故郷をあとにされたのか。それについて先生は次のように述べておられます。
「生活が苦しいから故郷を去るわけでもない。都会生活をあこがれるわけでもない。私は一家の中心であるけれども、たびたび故郷の老父を訪(と)うにはあまりに忙しい体である。しかるに両親は老いゆくままに、ただ私を杖とも柱とも思って生きている。私は私の自由なる活動を欲するために、老いたる両親に一日でも安堵した生活をさすために、家を閉じて出ることにしたのだ。」

先生は長男として、親に対する孝養とまだ幼い弟妹に対する養育の責任を決してなおざりにはされなかったのです。
十二月五日の先生はご家族と共に、祖先墳墓の地に立って、故郷を離れる決意を報告され、静かに合掌して「讃仏偈」を唱えられました。その「讃仏偈」の最後の四句「(仮令身止 諸苦毒中 我行精進 忍終不悔」)を幾回となく口の中で繰り返されて、下の道から出発の時を知らせる自動車の合図も、しばし耳に入らなかったそうです。その時の先生の深い感慨は、どのような言葉をもっても表わすことが出来ないことでしょう。
特に「讃仏偈」のこの四句は、法蔵菩薩が大誓願を説くにあたって、十方の諸仏に対して、私はたといどのような苦を身に受けようとも、一切衆生のために必ずこの念願を果たし遂げずにはおかないという一大決心を述べたものです。
〈たとい身をもろもろの苦毒の中に止(お)くとも、わが行は精進にして、忍びてついに悔いざらん〉、先生は、「私も故郷を後に、もろもろの苦毒の満ちた都会の地に飛び込まねばならぬ。・・・祖先を背に、社会を前に、私はどうしても法蔵のこの偈をわがものにせずにはおられない」と述べておられます。考えてみれば、夜晃先生の、仏法とサンガのために捧げつくされた白熱のご生涯と、光明団運動の原点はここにあったと言わざるを得ません。
それにしても、何のあてもなく、助力者もいない街に家族を引き連れて出て行かれたわけですから、その生活は大変でした。後にその当時のことを振り返って、先生は「さながら喪家の犬のように食うにも困る日が続く」と述べておられます。
赤手空拳、もとより一人の門徒もなく、定まった収入もなく、数人の家族をつれ、家賃(当時五十五円)を払っての生活は、想像することすら出来ないほど厳しいものでした。お母さんは当座をしのぐために度々質屋に通われなければならなかったり、先生もマニラ麻をつなぐ手内職をされた時もあったようです。
それからの約五年間は、先生のご教化が広島市を中心に周辺農村地帯に広がって、次第に本団の基礎が作られていった期間でした。本団の六十年史年表によると、この五年間の先生の東奔西走は特筆すべきものでした。請われるままに、連日のように農村を中心とした県内のあちこちをまわって説法獅子吼していかれました。
しかしそのご苦労は段々と実って、各地に次々と支部が出来、同胞も増えて、団の前途に大きな光を見出していかれたのもこの頃です。草創期の光明団と夜晃先生をしっかり支えた加計支部と福山支部もこの時期に出来ました。しかし本部は依然として借家住まいに変わりなく、初めは広島市外の三篠町に設けられましたが、翌年には市内の南竹屋町へ、さらに八丁堀へと、本部を転々と移されねばなりませんでした。

(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)