ご晩年の先生‐1
先生のご晩年とは、何年(何歳)からと考えたらよいでしょうか。これは人によって多少異なるかと思いますが、私は先生が満五十歳になられた終戦の年(昭和二十年)以後、お亡くなりになられるまでの四年間がそれにあたると考えています。
その根拠になると思われるものを一、二上げると、戦後の昭和二十一年に先生と遇われた、お同胞の故 辻 おふみさんの追憶文の中に、「『わしも五十になったので、そろそろむしろを巻いて帰りじたくをする』との(先生の)常のお言葉が耳に残っている。」とあります。
もう一つは柳田智照先生が、「昭和二十二年の八月、山口県連の開講にあたって、『むしろを巻いて帰る旅だ』との先生の一言にふれて、ギョッとした。死を直視しておられるみ心に照らされたからだ。」と「光明」誌に書いておられる文です。
どちらも先生ご自身が、もはやしっかり晩年の自覚を持って生きておられることを示す言葉ですから、戦後をご晩年と受け取るのは自然だと思います。また、日本の敗戦を通して、先生の念仏の道に対する信念が一段と深く強くなったのは前述の通りです。
先生の晩年において特筆すべき大きな事柄が二つあると思います。一つは、故郷を離れて二十五年ぶりに、郷里にお帰りになったことであり、もう一つは団創立三十周年を迎えられたことです。
① 先生、故山に迎えられる
昭和二十二年四月、先生五十三歳の時、郷里の原村(中原)への帰郷が実現しました。大法に乗托してでなければ故郷には帰らないと決意して、その時の熟するのをじっと待っておられた先生のお喜びは察するに余りあります。先生は
「思えば故郷を離れて二十五年、夢にさえ浮かぶなつかしの故里、故山も喜んで迎えてくれるであろう」( 実弟の蘇晃氏あての手紙)
と書いておられますが、まことに二十九歳の時、追われるが如く故郷を後にされて、その後帰りたくても帰れなかったのでした。安芸門徒の土徳の中にあって、新しい仏教改革運動に立ち上がられた先生を、郷里は決して受け容れようとはしなかったのです。ひとたび異安心というレッテルを貼られると、説かれている教えの内容(事実)よりもレッテルのほうが一人歩きしていくのは世の常です。
四月二十四日午前中に隣村の琴谷の西楽寺の会座を済まされた後、二十四日午後と翌二十五日の二日間、先生の生家のすぐ近くの本立寺で「六字釈」のお話をされました。黒板に達筆で板書なさり、聖典を開いて、驚くばかりのご説法だったそうです。柳田西信先生も、長女の公子さんも同伴しておられました。参加者は住岡家の親族を始め有縁の人々、隣村の同胞など三十名あまり、地元の人はやはり少なかったようです。実は本立寺のご住職は、初めは、すでに異安心の風評の立っている夜晃先生の法座を自坊で引き受けることをかたくなに拒んでおられました。それをお寺の門徒総代をしておられた岩見さん(斉藤タマ子さんの父上)が中心となって強く抗議してやっと実現したとのことです。しかし内陣には幕を張られて、本尊を礼拝することは出来なかったそうです。その時講師当番をされた斉藤さんは、先生の
「この村で一人でもよいから本当の念仏者が誕生したら大変なことがおこるよ」
という言葉を聞いて、ヨシその一人にならせてもらおうとひそかに決心したことを思い出すと述べておられます。
先生は翌年の七月十七・十八日の二日間、もう一度本立寺でお話をされました。前年の会座の後、関係者の努力によって原支部創立の話が持ち上がり、その原支部の発会記念法座が持たれたのです。講題は「歎異抄総結の文」でした。そのときは本堂は人で満ち溢れ、地元の人々も沢山お参りされたようです。
十七日の夜は先生の生家であった前岡さん宅で盛大な歓迎の宴が催されました。当時原中学校の先生であった亀岡定美先生も参加しておられて、その時先生の心の底に強く焼きついて離れない光景を紹介して下さいました。それは宴会の途中に、夜晃先生の実弟の住岡秋作先生がツト立ち上がって、涙と共にしぼり出すような声でトツトツと話された言葉でした。
「私の兄は、兄であって兄ではありません。私にとって兄は終生の師であります。・・・それは私ども弟妹、みなの心であります。」
それを聞いた宴席の一同はしばし沈黙して、静寂の空気が会場を包んだということです。
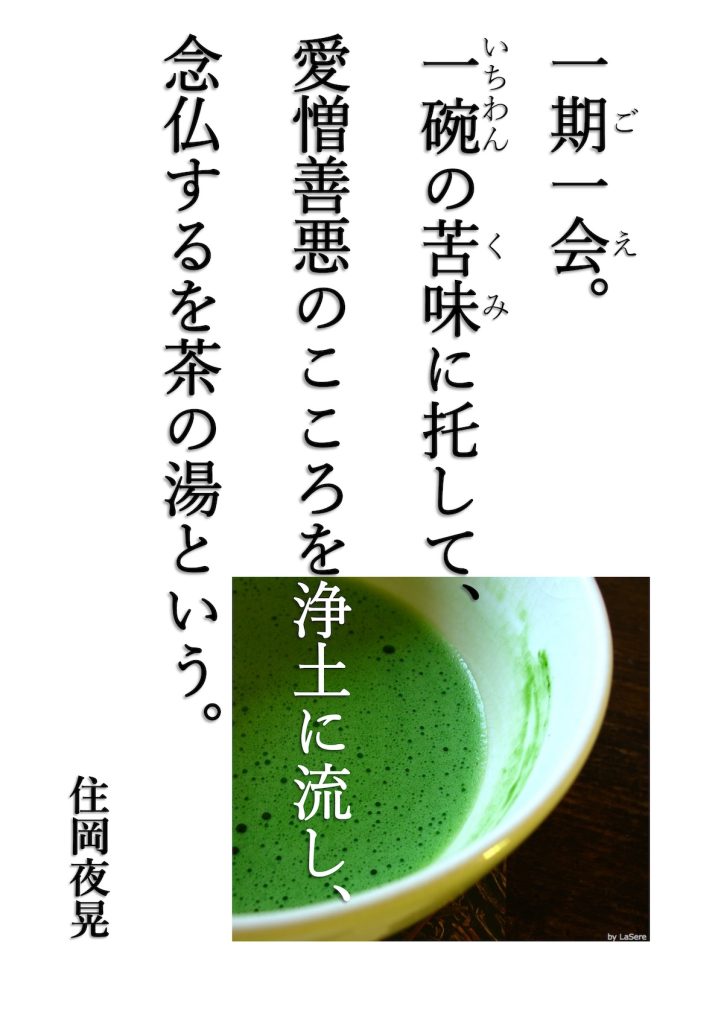
「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、[『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行]の文章を再掲載したものです。

